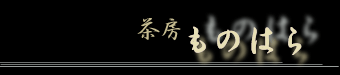
勇み足を恐れず、世間の非難と嘲笑も恐れずに仮説を紹介しましょう。それは長次郎一族です。
利休との関わり、人材、技術・理論の伝播共有、秘密の保持等々大変都合がよい。
次の最初の6を1576年、次の7が1577年以下同様に読んでください。
6789012345678901234567890123456789012345
1580 1590 1600
1586宗易形茶碗登場
―――利休―――――→1591没
――――――――――――――織部――――――――――――→ 1615没
-①初代長次郎-→1589没77才
* * * * * * * * * * * 二代長次郎 * * * * * * * * (二代長次郎は必ずしも明確ではないとの説。1615~24没か?
―――――――――――――――――――②常慶―――――――――――――――田中宗慶―――――→1595没60才
(利休の子で常慶、宗味の親)
――――――――――――――――――――宗味―――――――――――― * * * * * * * * * * 宗味の娘で二代長次郎の妻 * *
―――――③道入――――――
*1586宗易形茶碗登場
筒井定次伊賀上野へ。伊賀焼き焼成可能期(1585~1608)
←――――――――――――――――→
田中宗慶、二代長次郎、宗味、宗味の娘がどのような存在であったか楽家文書でも明らかでないところも興味をそそります。
なるほど。こういう切り口ですか。これは予想もできないことでした。当然、これからが本番でしょう。どうなるのでしょうか。
またまた、私が勘違いをしたのでしょうか。私はNO.1183は、さむしろさんがご高説を述べられるための資料の提示であると理解していました。しかし、今朝になってふと不安になってきました。あのままでは、なぜ、長次郎の茶碗が織部や志野などの大胆な茶碗へと発展していったのか、説明されていません。わずかに筒井定次の名前が出てきますので、伊賀焼は何らかの形で、長次郎焼と関係があるとお考えのようだということは推測できます。それにしても筒井定次と楽家との関係も明らかにされていません。こうした疑問がすべて私のあせりすぎで、これから本論に入ろうとされていたのなら、申し訳ないことです。
準備不十分なまま発表しましたのでわかりにくいと思います。年表からわかることは道入(のんこう)は時代的にはずれるということです。伊賀の制作年代が特定されると対象になる制作者も限られます。先に、したり尾さんから四方の楽茶碗の話がありましたが、伊賀にも四方を取り入れたものが多数あります。少し時間をいただきながらゆっくり述べさせて下さい。
分かりました。どうぞ、ゆっくり時間をかけて下さい。楽しみにお待ちします。
本論からは外れますが、現在楽家では、田中宗慶は、長次郎の妻の祖父にあたり、田中姓を名乗っていることから、利休と深い交流を持った人物で、長次郎の楽焼窯の、いわば一族共同経営者のような立場の人物と認識しているようです。利休の子という説もありますが、そこまでは楽家では踏み込んでいないようです。
いやいや本論からははずれません。重要な部分と考えています。田中宗慶の子常慶が楽家二代目です。又、宗慶の孫が初代長次郎の妻とすると、長次郎が1589年に77才で亡くなっていますが、このとき妻の祖父宗慶は54才となりますので長次郎より23才若い。妻の祖父としてはあまりに若く不自然です。このことが、二代目長次郎の存在説の論拠の一つのようです。
そうですね。少しおかしい。それでは、もう話しませんから、ゆっくりお話ください。
興味を持った記述を少し転載しましょう。日本の陶磁1長次郎・光悦(中央公論社)からです。暫く連載しますが、特に断らない限り同書からの転載です。昭和30年11月、陶磁協会大阪支部主催の長次郎展に際し、当代楽吉左衛門氏が楽家に伝来した文書中一入と宗入が相寄って記したらしい『覚』を発表し、長次郎、宗慶、宗味、常慶さらに宗味の娘で長次郎の妻であった人が存在したことが判明したのである。(つづく)
-略- したがって彼らの作品が長次郎作の茶碗として伝えられていたことになり、さまざまの作振りのものがあるのは当然のことと了解されたのであった。私もその座につらなっていたのであるが、今でもあの文書を拝見した時の一種独特の感情の高ぶりは忘れがたい。したがって、長次郎焼を考察するには、前記の文書はまことに重要であるので、ここに掲げておきたい。(以上転載。「前記の文書」はここでは転載しないので、興味のある方は日本の陶磁、長次郎・光悦をご覧いただきたい。 つづく)
-略- 発表された文書は系譜とその間の消息を伝えた『覚』一通と、それに従った『楽焼系図』一通、さらに法名を年次順に記したらしい『覚』一通の計三通の文書である。宗入筆であることは、『覚』の末尾に -略- と記していることであきらかである。(つづく)
資料をもとにした磯野氏による系図には単に「娘」としか記していない「宗味の娘で二代長次郎の妻」について「長次郎早死のゆえ実家に帰り尼焼を作る」と添え書きがある。(つづく)
お話の途中申し訳ありません。私はこの本を持っていませんので伺いますが、今引用されている文章をお書きになっているのはどなたですか。お名前を教えてください。それだけです。教えて頂いた上で、お話を続けて下さい。失礼しました。
解説、編集責任者 林屋晴三となっています。これによって、従来まったく記録の上からは抹消されていた宗慶が、宗味と常慶の父であったこと、さらに宗味と常慶が兄弟であったことが明らかになり、しかも宗味の娘が長次郎の妻であることがわかった。ところが、梅沢記念館に蔵されている「三彩獅子香炉」が宗慶の作であり、その腹部に「とし六十 田中 天下一宗慶(花押)文禄四年九月吉日」の彫銘があり、表千家伝来 -略- 利休の画像の賛に、大徳寺の春屋宗園が「常随 信男宗慶照之請賛」と記してあり、宗慶がいつも利休に随していた人物であること、そして彼の需めによって賛をしたためたことを記しているので、宗慶が楽家の系譜にとってまことに重要な人物であることが判明したのであつた。(つづく)
(注)ところどころを「拾い書き」していますのでそのつもりで読んで下さい。
ご安心ください。そのつもりで読んでいます。分からないところは、引用が終わった後、まとめて質問します。
『覚』は宗味の娘が長次郎の妻であったと伝えているが、文禄四年に六十歳であった宗慶の孫娘とすれば常識的に判断して、その頃おそらく二十歳を過ぎていなかったであろう。さらに長次郎の歿した天正十七年には十四、五歳の幼童でしかなかったことになり、初代長次郎の妻にするには不合理である。 (つづく)
宗慶作香炉が偽作と判断されないかぎり、『覚』にはなんらかの矛盾があるように思われ、 -略- 、長次郎には初代と二代があったと考察しうる可能性が強いのである。さらに、法名を列記した『覚』のなかに、長次郎、宗慶、宗味の間に長祐という人物が記入されているが、この人物は『楽焼系図』には見当らないのである。そうしたことから磯野氏は、この長祐こそ宗味の女婿に当たる長次郎すなわち二代目長次郎ではないかと推測したのであった。(つづく)
続-引用 以上のように、常慶以前の楽焼には、宗味の娘も作陶したとすれば、六人あるいは五人の人々が茶碗などを作っていたことになる。長次郎の茶碗にさまざまの作行きのものがあるのも当然のことであろう。ところが、こうした楽家の消息をすべて知っていたと思われる千宗旦が、その箱書などにも、また手紙にもいっさいふれていないのであり、また江岑や仙叟もその箱書には単に「長次郎」または「長次郎焼」と書しているのみである。楽家とはあれほど密接であった宗旦やその子供が、常慶以前の楽焼をすべて「長次郎焼」としているのはおそらく単なる無頓着ではなく、なんらかの理由があってのことと思えてならない。(つづく)
続-引用 それは後世楽焼の系図を長次郎、常慶、道入としてしまうことと無関係とはいえないようである。すなわち楽家を取りまく社会情勢に大きな変動があり、故意に宗慶や宗味が系図の上から後退させられる現象が起きたものと推測されるのである。『宗入文書』にふたたび目を移すと、庄左衛門宗味のところに「但宗味孫子素林寺ニ有候 太閤様より拝領の印 即双林寺ニ有候」と記されていることは注目される。文禄四年には「天下一宗慶」として香炉を作り、利休画像の賛を春屋和尚に依頼したりして、おそらく楽家の中心人物であった宗慶とその長男である宗味が、しだいに系図の上から消えていった原因を、前述のことは暗示しているようである。(つづく)
続-引用 常慶印の捺されているものに、一連の織部好みの茶碗と共通した沓形茶碗が造られていることは興味深く、あるいは黒織部となっているもののなかに、宗慶や宗味、常慶の作品が紛れていることもありえないことではない。有名な「島筋黒」などはその一例であり、かって古田織部の贈箱に収まった黒沓茶碗を見たことがあるが、それも楽焼に近いものであった。利休歿後から慶長末年までに、いかに楽焼とはいえ天下の茶風を担っていた織部の好みの茶碗を焼かぬはずはないのではなかろうか。(つづく)
続-引用 また宗味作と伝えられている茶碗が幾碗も残っているが、その判定はすべて後世のものであって、長次郎でも常慶でもないと判断したものを宗味としたようで、それらの伝承は極めて曖昧であるように思われる。(つづく)
鴻池道億が住友友昌に宛てた書簡のなかで、「惣別本長次郎と申ハ 七ツ八ツ有之様に覚候」と盛んに本当の長次郎は少なく、その他のものはすべて光悦だと述べているが、それはいささか過激な見解である。しかし、道億が長次郎の茶碗を焼いた人物が幾人もいたとは知らずに、「長次郎」と書付された茶碗を真剣に吟味したならば、利休以来のあらゆる条件が揃っている長次郎茶碗は七、八碗しか認められなかったことは肯ける。
以上で引用終わり。
これまで楽家は①長次郎②常慶③道入(のんこう)の理解でした。推測によるところもありますが、楽家の古文書から新しい疑問とともに多くのことが浮かび上がってきました。
これからが、さむしろさんのご意見ですね。どういうご意見をお持ちなのかお話ください。
「長次郎楽茶碗」や「織部様式茶陶」の制作について、次のようなことを考えています。 「長次郎楽茶碗」や「織部様式茶陶」の成り立ち論には、いくつかの事に合理的な説明ができる、あるいは少なくとも矛盾が生じないことが必要。制作年代は宗易形茶碗が現われた1586年頃(この数年前迄を含む)から1615年迄である。桃山茶陶には、アーティストによって制作されたものと職人によって制作されたものがあって、ここで論ずるのはアーティストの手によるものである。アーティストは複数人いる。(つづく)
賛成ですよ。
何らかのヒントからひらめいて三点展開による造形を確立した。複数の者がその造形技術を手中にした。複数の者がほぼ同時期(およそ30数年間)にその技術を手中にしたことは間違いないと思われるが、それぞれがその理論を発見したというより、最初に気付いた者がいて、他のものはその指導を受けた。と推測している。(つづく)
ここのところは、完全に同意見というわけではありません。特に『指導』という言葉が、少々引っ掛かるかな・・・。ひらめいたのは、長次郎でしょう? お続けください。
そうでしょうね。ここのところは考えが違うところです。長次郎を想定しています。それぞれの産地の窯場で作陶したであろうか? よそ者(京の人間)が、例えば備前へ行き、頼めば作陶させてもらえたであろうか? 多分、京あるいは京近辺で作陶したと考えているが、そうすると、あの時代に個人が伊賀、信楽、美濃、備前、唐津あたりから比較的簡単に陶土を取り寄せることができただろうか? 資料を調べればわかると思うが、例えば「焼き物奉行」などがいて管理されていたということはないか? もしそうであれば、相当な権力、財力を持ったものでないとむつかしいことになるのではないか?(つづく)
「焼き」を依頼するにしても同様のことがいえると考える。(つづく)
相当な名人であったはずだが、時代的に長次郎、常慶以外(楽家一族を除く)に名が残ったものが有来新兵衛の外に思い浮かばない。およそ30年間にわたって作られたと思われるが、名が漏れていない。名が漏れていないことが正しいとすると、相当に特殊な状況があったか、あるいはよほど強力な管理下にあったのではないか? 有来新兵衛についてはどのような関わりがあるのかわからない。(つづく)
NO.1212 NO.1213あたりで、時代状況に触れておられますが、織豊時代に限っていえば、少し認識が違います。例えば、この時代は関所が廃止され、人々の行き来はかなり自由でした。話が進んでしまう前に、念のため。失礼しました。お続けください。
楽茶碗や伊賀花入「生爪」、伊賀水指「破袋」について、利休や織部に是非ともほしいと所望した話などをみると、利休・織部を通じないと入手できなかったということの傍証とはならないだろうか? また、当時は相当な人気ブランドであったと考えてよいと思うが、完全に管理されていたのでなければ、商品としてもっと多くの織部様式茶陶が流通していてもおかしくない。(つづく)
「長次郎楽茶碗」や「織部様式茶陶」はいったん茶人の手に渡れば、出来が悪いとか好きではないなどといった理由で壊され失うということはないと考える。失うとすれば戦とか火事、地震の天災地変によるもので、世に出た後、災難にあわなかった茶陶は、現在知られているものと、人知れず旧家の蔵の奥に眠っているものでほぼそのすべてであると思う。つまり、そんなに多くの茶陶は作られていないと考えたい。(つづく)
以上のように「これは間違いない」といえるものは極めて少なく、いずれもかすかに残った事実と事実もどきから推測するしかない。「織部」が古田織部その人と焼きもの織部の両方の意味で用いられてきたことは間違いないし、当時の茶の湯界における織部の立場、伊賀水指破袋や伊賀花入生爪に関わった事実などから、古田織部が大きく関わったことも間違いないだろう。といっても直接の作陶をしたとは考えられない。そこで私の推測は、織部はプロデューサー的役割を担ったというものである。(つづく)
そして最後に大いなる推測であるが、織部が例えば備前から陶土を取りよせる。そして作陶家が織部屋敷に出向いて作陶する。出来上がると、織部が焼きようを指示して備前へ送る。備前から、焼きあがったものが出来の良し悪しにかかわらず織部宅へ送り返されてくる。織部の目利きをへて茶の湯道具となる。 このことは信楽、伊賀、美濃モノ、唐津についても同様であり、そしてその作陶家は楽一族ではないか。(完)