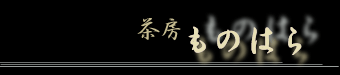
一方、戦国の若者たちの憧れは、一領一匹(あるいは一両一匹)の衆に成ることでした。
このことは、No.85においても少し記しましたが、「一両の具足甲冑と馬一匹」のひとかどの騎馬武者のことを指します。
そしてようやくNo.78に続くのですが・・・・
ここに上田宗箇(上田佐太郎、重安 関ヶ原以後浪々の身となり、剃髪して法諱 宗箇を名乗る)という武将がいます。武将茶人として知る人ぞ知るといった存在で、広島の茶道上田宗箇流の流祖です。
しかし、この上田宗箇という人物は、古田織部などとは正反対に、一番槍の名手として、戦国の世においては、大変な名声を博していました。
一番槍、一番乗り、一番首、先駆けの功名などと云ったものは、まさに矢玉の集中攻撃の中を、命を的に一揆に駆け抜けて行って功名を上げるのですから、命がいくつあっても足らない様な所業です。
上田宗箇という武士は、それを何度も実行し、功名を上げてきた歴戦の士だったのです。
つまり戦国乱世の当時においては、本人自身が、矢玉の集中砲火の中を、疾風の如く駆け抜ける鬼神の様な馬術、一騎打ちに打勝つ槍術や剣術、また組討にも優れた古武道、あるいは鎧通しの扱いに至るまでの、実践的武道における達人、つまり手だれの実戦的な兵法者だと云うことです。「宗箇老」と称されるのも「古参の老兵」と云う賞賛の意がこめられている訳です。
つまり例えば、戦国時代後期においての、個人としてのK1的な格闘界でのスタープレーヤー、あるいはヒーロー的な有名武将だったのです。
したがってこの上田宗箇などは、当時の若人達のみならず武将達にとっては、それは憧れや尊敬、畏敬の念を通り越して、軍神としての信仰と云ってもいいものでした。
例によって例えが悪いかもしれませんが、いわば唐獅子牡丹を背に咲かせ、白の晒しに長ドス引提げて鉄火場に出入りする高倉健といった類のカッコ良さなのです。(笑)
そしてこの慶長9年当時には、浅野幸長に招かれ、紀州で客分家老として一万石を給されていました。
上田宗箇が浅野幸長に招かれたのは、女系の縁戚関係からだと考えられます。
幸長の父である長政は、尾張の浅野長勝の養子として婿入りしたのですが、その妻の姉が木下藤吉郎(のちの太閤豊臣秀吉)に嫁いだ「ねね」(のちの秀吉の正室北政所、さらにのちの高台院)です。
そしてこの姉妹は、長勝がその妻の姉の娘を、浅野家の養女として貰い受けて養ったのでした。さらにその長政の妻姉妹の実家である杉原家の娘(ねねの従姉妹)が、上田宗箇に嫁いでいるといった具合です。
つまり「ねね」から見ると、浅野幸長は甥であり、上田宗箇は姪の夫に当たります。
また「ねね」は子が無かったので、加藤清正、福島正則らを養子として養育したのでした。
ご承知のことと存知ますが、関ヶ原において、豊臣恩顧の大名達のうち、これら浅野幸長、加藤清正、福島正則らが、家康の東軍に属したのは、「ねね」の威光であったとも云われています。
そう云う意味からすると、「ねね」すなわち「高台院」は、この慶長年間の影の立役者として、家康も一目置く、隠然たる権力を持っていたことが分ります。
家康が浅野幸長を紀州に封じたのは、大阪への先陣としての防御という意味合からだと考えられます。大阪城は難攻不落の大城塞ですが、強いてあげれば、南方がやや手薄だったらしいのです。そして先陣といえば、戦国一の先駆けの名手、上田宗箇をエッジの如く装填したという訳です。事実、上田宗箇は、後の大阪夏の陣、樫井の戦いにおいて一番槍の戦功を立てています。
つまり、淀君と秀頼の籠る大阪城への第一陣の備えとして、「高台院」系の縁者である浅野幸長、上田宗箇を配備したという訳です。「豆を煮るに、豆の皮を持ってする。」と云うセオリーを踏襲しているのでしょう。
したがって家康は、反面、彼らの情勢なり動向を常時監視しておく必要があると考えたことが、「浅野幸長に対して、『数寄の御成』の基本様式を工夫し、作成することを命じた。」真の目的だったのだ、と私は思うのです。
この慶長年間、我々は過去の歴史の一頁として史実を知っているので、不思議に感じないだけだと思うのです。
この時代、大きな戦こそありませんが、もし淀君が先に死んでいたら? もし家康が死んで如水が生きていたら? もし高台院が早く死んでいたら? などと仮定を変えてみると、歴史は簡単に大きく塗り変わりそうです。正に、一寸先は闇の、緊張したサバイバルゲームをしていたのでした。
上田宗箇と古田織部は、文禄元年の文禄の役において、肥前名古屋城において同行しています。また文禄2年には、徳川家康、古田織部、上田宗箇は、明使饗応の場に揃って参列しています。さらに伏見城下の各屋敷での茶の湯を通じた交流も元々盛んでした。
さらには、宗箇と織部は、慶長4年7月に、大徳寺三玄院の春屋国師からそれぞれ「宗箇」、「金甫」号を授かっています。
この様に、宗箇と織部は、その性格と生き様においては、かなり異なっているのですが、極めて親しかったことが推察できます。
そこでここに登場するのが、上田宗箇と古田織部と云えば、なんと云っても、伊賀焼の名品花入れ『生爪』です。
宗箇が織部に愛蔵の花入れを所望し、そこで織部は、生爪を剥すほどの思いで、これを宗箇に贈答したという添状があるものです。
No.100に記した我々の推理によると、
これはここで、「徳川方における 『文化的特殊兵器』 の一つとして使用された。」と云うことに成ります。
添状からは、これが織部から宗箇に送られた年については、ハッキリ特定できない様です。
私は、もしかしたら「慶長18年に浅野幸長が没した直後頃ではないか?」と云う気がするのですが、いかがでしょうか?
それは当時、徐々に大阪攻めに向かって動き始めていた頃であり、宗箇を何としても、紀州に繋ぎ止めておく必要があったからです。
たまたま縁があって、この『生爪』と云われる花入れを、22・3年前に、拝見したことがありました。それは如何にも戦国のヒーロー戦士が好みそうな、艶めかしさと潔さを感じさせる物でした。
『生爪』が登場したので、関連して、伊賀・伊勢の領主であった藤堂家伝来の、伊賀耳付水指の名品『破れ袋』について少し記します。
古田織部が、大野主馬(治房)に宛てた添状に「内々御約束之伊賀焼ノ水指令進入候 今後是程のものなく候間 如此侯大ひゞきれ一種侯か かんにん可成と存候」とあることから、おそらく織部が指導して創作させた伊賀焼の水指を、古田織部から大野治房に進呈したものと考えられます。
大野治房は大野修理治長の弟で、淀君の乳母である大蔵卿局の子であったことから、兄弟で豊臣秀頼に仕えた、当時は大阪方の中心的人物の一人です。
これも添状からは、進呈された年については、ハッキリとは特定できませんが、もしかしたら大阪冬・夏の陣の起こる前年、やはり慶長18年頃ではなかったのでしょうか?
例によって「全くの推理と私見」を逞しくしますが、どうも私には、進呈されたのがこの時期だったのだとすれば、「この作品には何かのメッセージが籠められているのではないか?」と云う気がするのです。
この頃の徳川幕府方は、もう明らかに大阪攻めと、豊臣家の覆滅を意図して準備していました。そこで大野兄弟を主戦論へと誘導しようとしていたのです。
そうだとしたらメッセージは、「決別。と、堪忍袋の尾は切れた。」でしょうか?
あるいは「大城塞、大阪城の壊滅。」を暗示したのでしょうか?
なお、古田織部の四男の九郎八 重行も、大阪城にあって豊臣秀頼の家臣でした。
またこの他にも、家康の近習で、後に京都所司代となった板倉重宗に瀬戸黒茶碗を贈った添状などがあります。
いずれにしても、このように桃山茶陶の名品は、織部から諸大名に贈られて行ったのでした。
「誰ゆえに 然(さ)のみ身を 尽くすらん。」
「船つなげ 雪の夕べの 渡し守。」
織部が宗箇との話しのついでに(「慶長御尋書」にて)、その心中を吐露した引用歌です。
古田織部から上田宗箇に贈られた「生爪」花入です。
上田家伝来の花入として「生爪」が有名ですが、唐津花入も伝来しています。左の写真の花入がそうですが、織部様式の造形がなされていると思われます。大変な名品であると思います。
いつの時代に上田家に入ったか不明ですが、光禅さんはなにか聞かれたことがあるでしょうか?
この花入について、安倍さんの意見を聞いたことがありませんので是非聞いてみたいと思っています。
NO124の唐津花入によく似た花入がもう一点あります。
「筒形の胴は四方に矯めて方形をなし」と説明があります。
伊賀にある四方形との共通性を感じます。
長次郎楽茶碗にも四方形(ムキ栗)があります。
NO125の花入には、口部内側に「新五郎」の彫文字があります。
新五郎が何者なのかわかりません。唐津の陶工あるいは京都・三條のいま焼き工人のなかに新五郎なるものがいれば大変わかりよいのですが。「依頼主の注文によって彫り込んだのではないか」との解説がありました。
少し視点を変えて、美濃の桃山茶陶について記してみます。そして美濃焼と唐津焼との交流、について少し考察してみようと思います。
古田織部は、美濃の生まれと云われています。しかし美濃のどこなのかは、どうもはっきりしない様です。いずれにしても、織部は美濃が生国であり、元々かなりの地縁があった様です。
美濃で、いわゆる織部焼が焼き始められたのは、慶長10年(1605)頃と云われています。
また志野は天正13年(1585)頃からとされています。なお黄瀬戸はそれよりも以前から焼かれ始めた様です。
この黄瀬戸の後に灰志野が現れ、鉄絵を描いて高温で焼いても、模様が流れて消えてしまうことが無くなったことから、我が国最初の絵付けされた焼物が、この美濃で生み出されたとされています。
この当時の、絵付けの新技術が、やがてさらに進化して志野、織部として、様々な文様が描かれる様になっていったのでした。
しかしこれら志野、織部ら美濃の桃山古陶に描かれた多種多様な文様は、それまでの灰志野などの頃とは、慶長10年頃を境として全く一変しています。
つまりこのことは、京都から画工が新たに参画していたものと考えられます。それまでの美濃の絵付けが、指導によって一挙に上手になったのではなく、全く基礎の違った上級の絵付師が参画したからです。
そしてこれらの焼物は、元和元年の古田織部の切腹を境として、突然パッタリと途絶えています。これは明らかに、織部が主体的に強力な主導権を持って、その制作を指導していたことを物語っています。
なお、これらの窯は、その後、尾張徳川家のお庭焼である御深井焼の生産拠点となって行った様です。
そしてこれらの美濃の絵付けは、同時代の絵唐津にも共通して、例えば網干文様等の同じ手の文様が多数存在します。
つまり、美濃 ⇔ 京都 ⇔ 唐津 の関係がそこにみられる訳です。